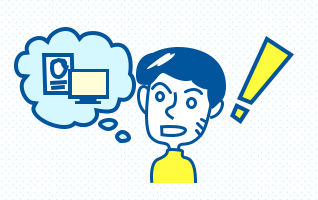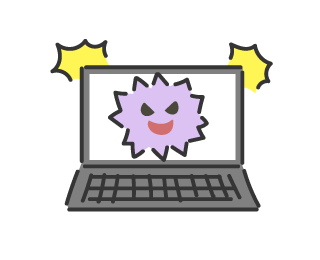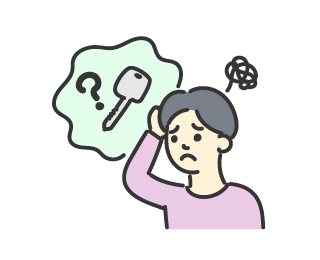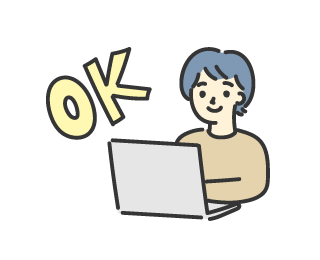生活道路におけるゾーン対策「ゾーン30」「ゾーン30プラス」の概要
生活道路対策の必要性
過去10年間の大阪府下における交通事故(人身事故)発生件数は、減少傾向にありますが、全交通事故件数に占める車道幅員5.5メートル未満の道路(統計上の生活道路)における交通事故発生件数の割合は、ほぼ横ばいで推移しています。
交通事故発生件数と車道幅員5.5メートル未満の道路の交通事故発生率の推移

令和4年中の大阪府下における状態別の交通事故死傷者数をみると、車道幅員5.5メートル未満の道路における歩行者・自転車乗用中の死傷者が占める割合は、車道幅員5.5メートル以上の道路の約1.5倍でした。
車道幅員別・状態別の交通事故死傷者の構成率(大阪・令和4年中)

「ゾーン30」
ゾーン30とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の区域規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する車両の抑制等を図る生活道路対策です。
「ゾーン30」における主な対策内容
~対策のポイント~
- ゾーン内における走行速度の抑制
- 通過交通(抜け道としての通行)の抑制、排除

「ゾーン30プラス」
生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るため、ゾーン30プラスでは、最高速度30キロメートル毎時の区域規制のほか、交通実態等に応じて区域内における大型通行禁止、一方通行等の各種交通規制を実施するとともに、ハンプやスムーズ横断歩道等の物理的デバイスを適切に組み合わせて交通安全の向上を図っています。
「ゾーン30プラス」における主な対策内容

「ゾーン30プラス」の取組フロー

「ゾーン30プラス」に関するよくあるご質問
質問1 「ゾーン30」と「ゾーン30プラス」の具体的な違いは何ですか?
回答1
「ゾーン30」は、警察(公安委員会)による最高速度30キロメートル毎時の区域規制が主な対策でしたが、「ゾーン30プラス」では、道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携しながら、最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図り、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備に取り組むものです。
質問2 物理的デバイスを設置するとどのような効果が期待されますか?
回答2
ハンプやスムーズ横断歩道は、30キロメートル毎時を超えて走行する車両の運転者に不快感を与えることで速度や抜け道利用を抑制する効果が期待できます。また、スムーズ横断歩道を設置した箇所では、自動車が、横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者等へ道を譲る確率が向上することが確認されています。狭さくやシケインは、道幅の一部を狭くしたり、カーブさせた形状としたりすることで、車両の走行速度や抜け道利用を抑制する効果が期待できます。
質問3 物理的デバイスを試験的に設置することは可能ですか?
回答3
取り外し可能なハンプやロードコーン等を活用することにより、物理的デバイスを試験的に配置することが可能です。(国土交通省では、地方公共団体へ取り外し可能なハンプの無料貸与を行っています。)
なお、いずれも設置するには課題等がある道路の道路管理者に相談していただく必要があります。