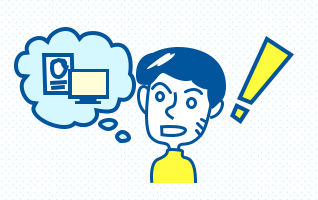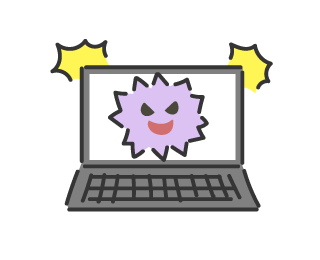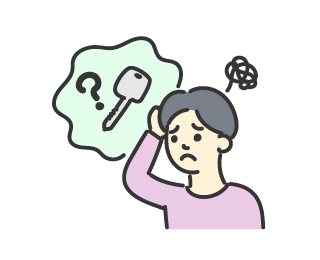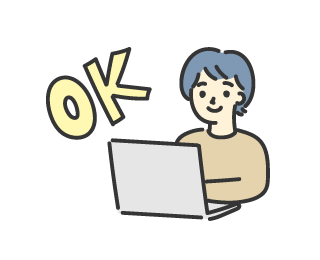ハンプ等の設置による交通安全対策
平成29年8月、大阪府豊中市柴原町付近の通学路にハンプが設置されました。
これは、平成27年5月に発生した交通事故の発生を受け、豊中市と大阪府警が連携して交通安全対策の検討を進め、事故現場周辺にハンプの設置や歩道、横断歩道の整備などの対策を実施したものです。
ハンプとは
ハンプとは、道路上に設けた凸部(コブ状のもの)で、生活道路等における車両の速度抑制のために設置されます。

上記写真は、平成29年8月に豊中市柴原町付近に設置されたハンプ
ハンプの効果
生活道路等においては、車の速度を時速30キロメートル以下にすることが交通安全対策として有効とされています。
これは、車と人との交通事故の場合、時速30キロメートルを超えると歩行者の致死率が急上昇するためです。
ハンプの上を車が速度を(時速30キロメートル以上)出して通過すると衝撃による不快感があるため、ドライバーがハンプを事前に認識することで車の速度を抑えて走行するようになる効果が期待できます。

ハンプの構造
凸部はその端部から頂部までの部分(傾斜部)及び凸部の頂部における平坦な部分(平坦部)からなり、その構造は、
- 平坦部の長さ: 2メートル以上を標準とする
- 凸部の高さ: 10センチメートルを標準とする
- 傾斜部の縦断勾配: 平均で5%、最大で8%以下を標準とする
- 傾斜部形状: 凸部を設置する路面及び平坦部とのすりつけ部を含め、なめらかなものとする
となっており材料は、耐久性があり、車両及び歩行者の安全な通行が確保できるものを用いることとしています(国土交通省「凸部、 狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」から引用)。
それ以前については、特に基準は定められておらず様々な形状のハンプがあり、騒音や振動を生ずるものもあったため、国土交通省が基準を定めました。

国土交通省ホームページ「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」から引用
ハンプを通過する車両の様子
豊中市に設置されたハンプ上を走行する車両の多くは、ハンプの手前で減速して通過しており、ハンプ通過に伴うに振動や騒音は特に感じられませんでした。

上記写真は、平成29年8月に豊中市柴原町付近に設置されたハンプを車が通過する様子